企業訴訟の基礎知識
未公開株式の株価算定方法(中小企業における株式買取請求紛争)
上場株式であれば、証券取引所において多数の市場参加者による多数の取引の集積を通じて、その時々の適正な株価が形成されています(もっとも、上場株式についても、合併、株式交換、株式公開買付(Take Over Bid, TOB)の場面等では、会社の支配権や当事会社間の事業のシナジー(Synergy、相乗効果による追加的価値)等の評価に関連してその株価についても争いが生じます。)。
これに対し、未公開株式の場合、(1) 投資家が新たに株主として出資をする場面(第三者割当増資)、(2) 株式を譲渡する場面、(3) 株式を相続する場面、(4) 複数当事者による共同事業(Joint Venture、JV)を解消する際に株式を引き取る場面、(5) 株式譲渡制限会社(株式の譲渡に取締役会等の承認を必要とする会社)において、会社が当該譲渡を不承認とした際に、株主が株式買取請求権を行使する場面、(6) 合併、株式交換等に反対した株主が会社法の規定に基づき株式買取請求権を行使する場面、等いろいろな場面で、その株価が問題となります。
また、未公開株式を巡る詐欺等のトラブルが後を絶ちません。これも未公開株式の株価が判然としないことに一因があるといえます。
では、未公開株式の株価の算定はどのように行われるのでしょうか。会社法上は、上記(5) の株式譲渡制限会社において、会社が譲渡を不承認とした際に、株主が株式買取請求権を行使した場合、その買取価格を裁判所が決定するときは、「承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない」(会社法144条3項)と定められています。また、会社法上、上記(6) の合併、株式交換等に反対した株主が株式買取請求権を行使した場合の買取価格は「公正な価格」(会社法785条1項、806条1項)と定められています。しかし、いずれも具体的な価格算定方法は明らかではありません。本稿では、これらの株式買取請求権が行使され訴訟となった最近の裁判例をご紹介します。
なお、相続税に関する財産評価基本通達において、相続税額を算出するための詳細な未公開株式の評価方法が定められていますが、一般的に評価額が低めになり、株式買取請求権行使の際の株価評価方法としては適切ではないため、本稿では類似業種比準方式の簡単な紹介にとどめることとします。
未公開株式の株価算定には、多様な方法があります。以下では、代表的な算定方法の概要をご紹介します。結論的にはいずれも一長一短があります。
会社の純資産(総資産の額-総負債の額)を基にして、株価の算定を行う方式です。帳簿(貸借対照表(B/S))上の純資産を基にするため、客観性に優れています。しかし、市場取引における実勢の反映の点に問題があるほか、知識集約型・労働集約型の会社の収益獲得能力等が反映されない点に問題があるとされています。一般に、清算が予定されている会社の株価(清算価値、Liquidation Value)の算定に適しているといわれます。逆に、今後も永続的に運営されることが予定されている会社の株価(継続企業価値、Going Concern Value)の算定には難があります。基準となる純資産額の算出方法により、簿価純資産法、修正簿価純資産法、時価純資産法に分かれます。
1株の価格 = 簿価純資産額 ÷ 発行済株式総数
簿価純資産額とは、会計帳簿上に記載されている資産から負債を控除した純資産額のことです。
1株の価格 = 含み損益を加味した簿価純資産額 ÷ 発行済株式総数
会計帳簿上の純資産額を基本にしながら、含み損益を評価に加味して株価算定を行います。含み損益を評価に加味するので、簿価純資産法より評価時の実態的な資産価値が反映されます。しかし、含み損益の額につき当事者間で評価が割れる可能性があります。
1株の価格 = 時価純資産額 ÷ 発行済株式総数
時価純資産額とは、時価評価された資産から時価純資産額を算出する純資産額です。しかし、全ての資産を適切に時価評価することは困難であり、紛争当事者間でその適切性が争われることになります。
会社のキャッシュフローを基に株価の算定を行う方式です。キャッシュフローとは、税引後の純利益に減価償却費等を加算した上で、資本支出額(事業の継続に必要な不動産、設備等の取得に要する金額)を控除した額を指します。将来の収益獲得能力等を株価に反映する点で優れていますが、収益能力算定の基礎となる、キャッシュフローの算出等に恣意性が入る点が問題とされています。キャッシュフローについて、DCF法は会計上の収入として考え、収益還元法は利益として考えます。
1株の価格=(将来予測される単年度の税引後純利益÷資本還元率)÷発行済株式総数
将来獲得すると予想される1年分の税引後利益を、資本還元率という特殊な数値で還元して、株価を算定する方法です。
「資本還元率」は、市場金利・長期国債利回り・評価対象会社の調達金利等を基に、これに危険率を加味した上で決定されるとされ、また、「危険率」は、評価対象会社の規模・業種・経営環境・市場動向・カントリーリスク等を総合的に判断して決定するとされます。しかし、将来予測に基づく単年度の税引後純利益や、種々の要素を総合的に勘案する資本還元率は、いずれも、紛争当事者間で納得のいく数字に収斂することは困難といえます。
1株の価格=将来予測される年度別収益を現在価値に割引いた合計÷発行済株式総数
会計帳簿上の利益ではなく、将来予測される年度別収益(フリーキャッシュフロー)を現在価値に割り引いて、株価を算定する方法です。会計帳簿上の利益では、実際には出金がないにもかかわらず減価償却費が控除され、他方、貸借対照表の資産として計上される資産の取得費は一時に出金がなされるにもかかわらず、初年度の減価償却費を除き、費用として控除されません。これに対し、フリーキャッシュフローは、現実の出入金に合わせた調整を行うことになります。また、DCFでは、1年後の予想収益、2年後の予想収益、・・・n年後の予想収益とn年後に解散した場合の予想残余財産額を具体的に想定する点で、収益還元法(直接還元法)よりもきめ細かいといえます。
「将来予測される年度別収益を現在価値に割引いた合計」(PV、Present Value)は以下により算出されます。
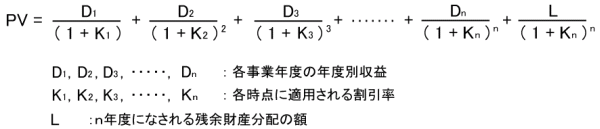
しかし、将来予測に基づく年度別収益や、それを現在価値に割り引くための「割引率」(一般利子率にリスク・プレミアムを加えた割合をいい、資本還元率に類似した概念です。)については、やはり紛争当事者間で納得のいく数字に収斂することは困難です。
DCF法の詳細は、江頭憲治郎教授の「株式会社法(第4版)」のpp.15-18に譲ることとし、ここでは「現在価値に割り引く」という考え方について簡単に説明したいと思います。
(A)現在1万円の配当をもらうことと、(B)1年後に1万円の配当もらうことを比較する場合、(A)の1万円で直ちに国債購入又は銀行預金をすれば、1年後には利息が付くので、(B)よりも(A)の方が得であることはすぐに理解できると思います。そして、現実の企業を想定すると、1年後には業績が悪化し配当が1万円に満たなかったり、1年以内に企業が倒産したり、赤字になって配当が全くもらえなくなったりするリスクも考えられます。このようなリスクも勘案した上で、「1年後の1万円」÷(1+r)=「当該1万円の現在の価値」と評価することができるrを「割引率」といい、1年後の1万円を1+rで割って、現在の金銭的価値を算出することを「現在価値に割り引く」といいます。
仮に割引率を10%とすると、1年後の1万円の現在価値は、
1万円÷(1+0.1)=9090.90・・・
で、約9091円になります。
現在価値への割引は複利計算で行うため、2年後の1万円の現在価値は、
1万円÷(1+0.1)^2 = 1万円÷1.21 = 8264.46・・・
で、約8264円になります。
将来予測される株主が獲得する配当に着目して、株価の算定を行う方式です。配当のうち内部留保分を算定の考慮に入れるかによって、配当還元法、ゴードン・モデル法に分かれます。いずれも、資本還元率を始め、算式の各要素が一義的に収斂しないことが難点です。
1株の価格=(将来予測される年間配当額 ÷ 資本還元率)÷ 発行済株式総数
配当を継続して行っている会社では有効ですが、年間を通じて継続した配当を行っていない会社では、配当を予測することが困難であるため、この算定方法は向きません。
1株の価格=将来予測される年間配当金÷(資本還元率-投資利益率×内部留保率)
内部留保された利益が将来利益を生み、配当金は一定割合で増額するという仮定した上で、配当金の内部留保分の性質を考慮し、株価に反映させます。
投資利益率(Return on Interest、ROI)とは、投資金額に対し1年間に生み出す利益(税引後純利益)の額の割合をいいます。内部留保率とは、税引後当期純利益のうち、株主への配当に回さず、会社内に留保して利益剰余金として計上する割合をいいます。
類似の会社、事業の資産や利益等の複数の比準要素を比較することによって株価を算定する方法です。適切な比較対象となる上場会社が複数ある場合には、市場での取引環境の反映ができ、有効な算定方法といえます。しかし、同業種内での浮沈が常である現実を勘案すると、比較対象との比較の合理性には疑問が残ります。
相続税に係る財産評価基本通達にある類似業種比準方式における基本的な算式は以下のとおりですが、さらに様々な調整が行われます。
1株の価格=A×〔(b÷B)+(c÷C)×3+(d÷D)〕÷5×斟酌率
| A | 類似業種に属する会社の平均株価 |
|---|---|
| b | 被評価会社の1株当たりの配当金額 |
| B | 類似業種に属する会社の1株当たりの配当金額 |
| c | 被評価会社の1株当たりの利益金額 |
| C | 類似業種に属する会社の1株当たりの利益金額 |
| d | 被評価会社の1株当たりの純資産額(簿価) |
| D | 類似業種に属する会社の1株当たりの純資産額(簿価) |
| 斟酌率 | 大会社の場合 0.7、中会社の場合 0.6、小会社の場合 0.5 |
このように株価の算定方法は多数あり、いずれも一長一短があります。そのため、過去の裁判例でどのような判断枠組みが採用されているかが重要な意義を有します。過去の多くの裁判例では、複数の評価方法により算出された金額を一定割合で加重平均した株価を採用しています。これに対しては、「一つ一つが信頼に値しない数値を複数寄せ集めたからといって、信頼できる数値が算出できるわけのものではない。」(前掲・江頭15頁)との厳しい批評のあるところですが、以下では、株価の算定方法が争点となった近時の裁判例を紹介致します。
株式譲渡制限のある未上場会社(大手清掃具レンタル業者である株式会社ダスキン)において、少数派株主の譲渡承認請求を会社が承諾せず、株主が株式買取請求権を行使したものの、株主と指定買受人との間の協議が整わず、株式買取価格の決定が申し立てられた事件です。第一審裁判所は、配当還元方式のうちゴードン・モデル法を採用しました。
本決定は、原決定と同様に、配当還元方式のうち、利益および配当の増加傾向を予測するゴードン・モデル法によるのが適当であるとしました。本決定は、株価算定を行った各鑑定のうち、原決定が採用した鑑定とは異なる鑑定を採用した点で原決定に変更を加えました。
本件は、株式譲渡制限のある非上場会社(デジタルコンテンツ配信事業)において、株主(申立人)の譲渡承認請求を会社が承諾せず、他の株主(相手方)が買受人に指定されたところ、買取価格について合意に至らなかったため、売買価格の決定が求められた事件です。本件は、鑑定によらず、裁判所が独自に株価を算定した点に意義があります。
本件会社は、平成14年9月から事業を開始し、相手方が3600株(60%)、申立人が2400株(40%)を保有しており、申立人の2400株全て(本件株式)が譲渡の対象になっていました。
第一審裁判所は、本件会社は、清算が予定されておらず、今後の収益も見込めること、また、含み益がある不動産が存しないこと等を考慮すると、収益還元法が算定方法として相当であると判断しました。
本決定は、収益還元法のみを算定方法として採用した第一審の判断を支持し、抗告を棄却しました。
本件は、株式譲渡制限のある非上場会社において、株主の譲渡承認請求を会社が承諾せず、会社自らが買い受けることとしたが、買取価格について合意に至らなかったため、裁判所に売買価格の決定が求められた事件です。
資本金1億2000万円、発行済株式総数240万株、株主資本約71億円、総資産約120億円、直近3期の売上高約60億円の会社でした。
株主は、議決権比率で26.17%を保有していますが、法令上の「支配株主」ではありません。
そして、株主側は、DCF法による株価(5481円から6097円の平均額5789円)と純資産方式による株価(4921円)を1対1の加重平均によるべき(4921円)と主張し、会社側はDCF法による株価(2038円から2640円の平均額2339円)とゴードン・モデル法による株価(376円から447円の平均額411円)を1対1の加重平均によるべき(1375円)と主張していました。
本件は、株式譲渡制限のある非上場会社において、株主の譲渡承認請求を会社が承認せず、会社が指定した買取人と株主の間の売買価格の協議が調わなかったため、裁判所に売買価格の決定が求められた事件です。
原決定は、DCF法を、事業収支計画の予測や投資利益率の決定が困難であるとして排斥し、平成17年3月期決算及び平成18年3月期決算に基づく純資産価額法による各株価の中間値である7万5000円を株価としました。
本件は、会社法施行前の商法第245条の5に基づき、事業譲渡(営業譲渡)の株主総会での承認に反対した株主が株式買取請求権を行使したものの、会社との協議が整わず、株式買取価格(「営業ノ重要ナル一部ノ譲渡ニ係ル契約ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格」)の決定が申し立てられた事件です(いわゆるカネボウ株式買取価格決定申立事件)。
第一審裁判所は、継続企業の価値の算定にあたってはDCF法が適切であると判断しました。
このように、近時の裁判例は、DCF法を株価算定の基本としながらも、あくまでも事例ごとに算定方法の相当性の判断を行っており、結論的には、株式買取請求訴訟における未公開株式の株価は、裁判官の裁量により算出されるといえます。そのため、裁判官を説得するための、高度な主張・立証技術が重要になります。
当事務所には、未公開株式の株価算定について豊富な知識と経験を有する弁護士が在籍しており、訴訟での複雑な主張立証にも対応が可能です。未公開株式の株価算定について、お悩み・ご質問がありましたら、日比谷ステーション法律事務所(03-5293-1775)にご相談下さい。
東京都千代田区丸の内3丁目4−1
新国際ビル4階418区
TEL:03-5293-1775
FAX:03-5293-1776